民事調停 世界に例のない制度がどのようにして形成されたのか
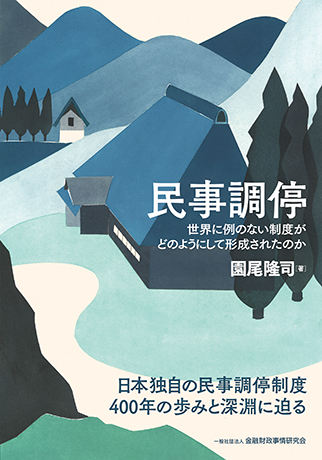
定価:3,300円(税込)
編・著者名:園尾 隆司[著]/藤田 圭子[史料収集・写真撮影]
発行日:2025年10月07日
判型・体裁・ページ数:A5判・上製・136ページ
ISBNコード:978-4-322-14616-5
書籍紹介
日本独自の民事調停制度
400年の歩みと深淵に迫る
◆「村上水軍」「パロマ」に続く、園尾隆司氏の第三作。世界に例をみないわが国の民事調停制度はどのようにして形成されたのか。40年間裁判官として民事裁判に関わった筆者が、民事調停制度発足100周年(令和4年10月)を機に、江戸時代前期に形成されたわが国の民事調停制度の歴史と現在の問題点を紐解く。
主要目次
第1章 民事調停との出会い
山間僻地で民事調停と出会うまで/「チョーテイ」との出会い/「チョーテイ」の真相/山間僻地から見えてくる民事調停制度の特質
第2章 民事調停の特徴
調停機関が裁判所内に設置されていること/調停委員の手当が低額であること/当事者本人に出頭義務があること
第3章 民事調停の起源に関する学説とその問題点
調停の起源についての思いがけない質問/相対済令説/和与説/ドイツ調停所説/民事調停の起源について適切な学説がない理由
第4章 江戸時代の裁判制度
江戸奉行所における裁判制度/江戸時代の村町役人制度/裁判前の村町役人の関与と役割/調停前置の手続/裁判受理後の職権付調停/職権付調停実施後の裁判手続/裁許の言渡しと当事者による裁許状の書写
第5章 公正な裁判の実現のための江戸幕府の諸制度
同一管轄区域に2奉行所を創設/評定所の創設/奉行への賄賂が消滅した時期/評定所制度と明治以降の不服申立制度との対比
第6章 江戸時代の調停制度の明治時代への承継
明治当初の訴訟・調停手続/明治以降の法廷の変遷と裁判・調停の手続/登米治安裁判所の法廷に見る明治当初の裁判・調停の実情/村町役人制度及び調停前置制度の廃止
第7章 勧解制度の創設から廃止まで
訴訟事件の急増と勧解制度の創設/勧解吏制度に移行後の勧解制度の衰退/明治民事訴訟法の施行による勧解制度の廃止
第8章 民事調停制度の創設と戦前における発展
民事調停立法の先駆け「借地借家調停法」の制定/江戸時代の調停前置制度に備わった3要素の承継/その他の借地借家調停法の特徴/民事調停制度の起源に関して適切な学説が形成されなかった原因/借地借家調停法に続く民事調停関係立法の数々
第9章 民事調停制度の戦後の発展
各種調停法の民事調停法への一本化/家事調停手続の独立手続化/非常勤国家公務員化による調停委員への報酬支給
第10章 民事調停制度の問題点とその克服の方向性
民事調停制度の問題点/専門性が不十分な問題の克服策の現状/低額の報酬問題の克服策の現状/職権主義の弊害の克服策の現状/民事調停の問題点克服の方向性